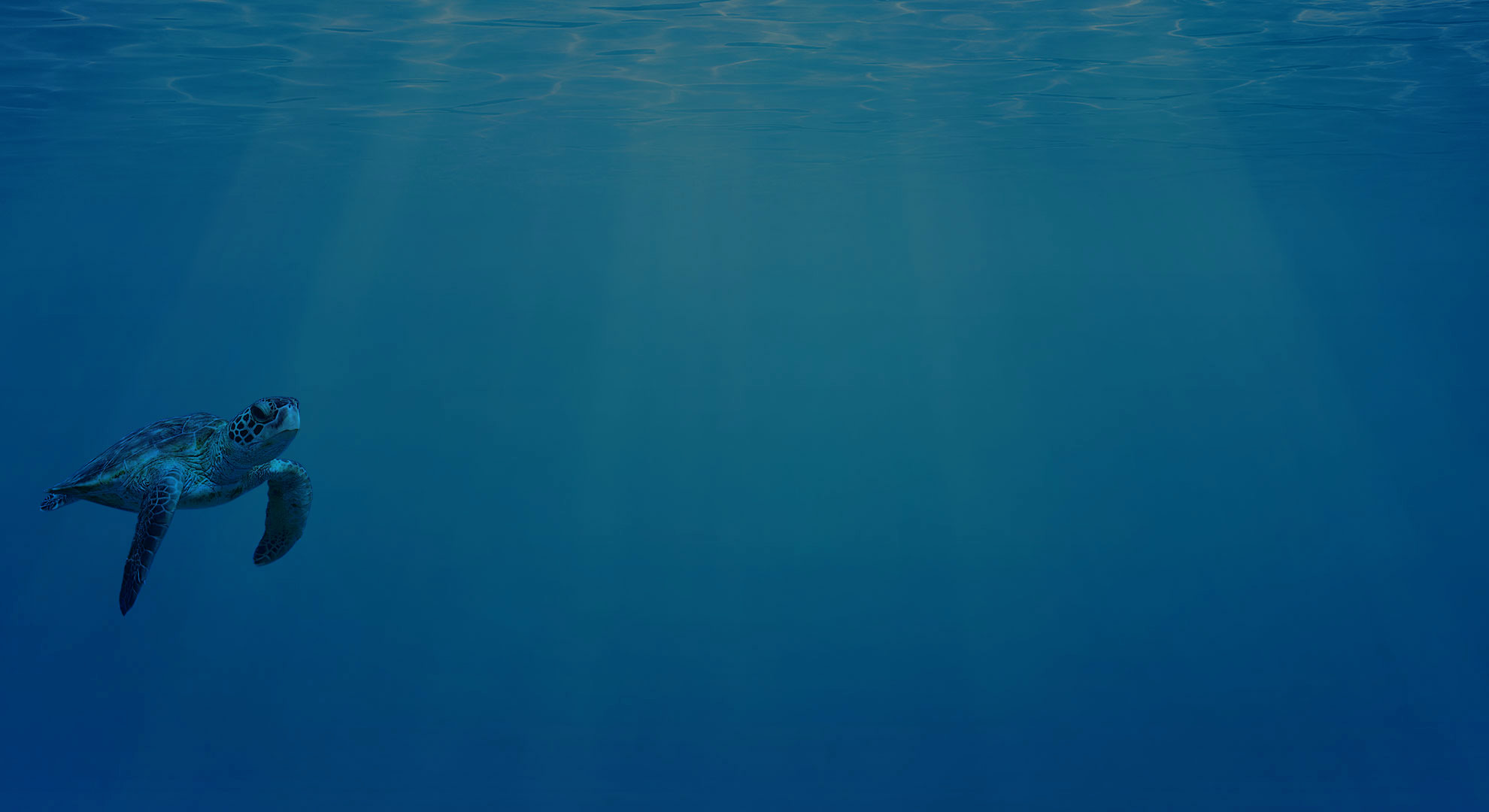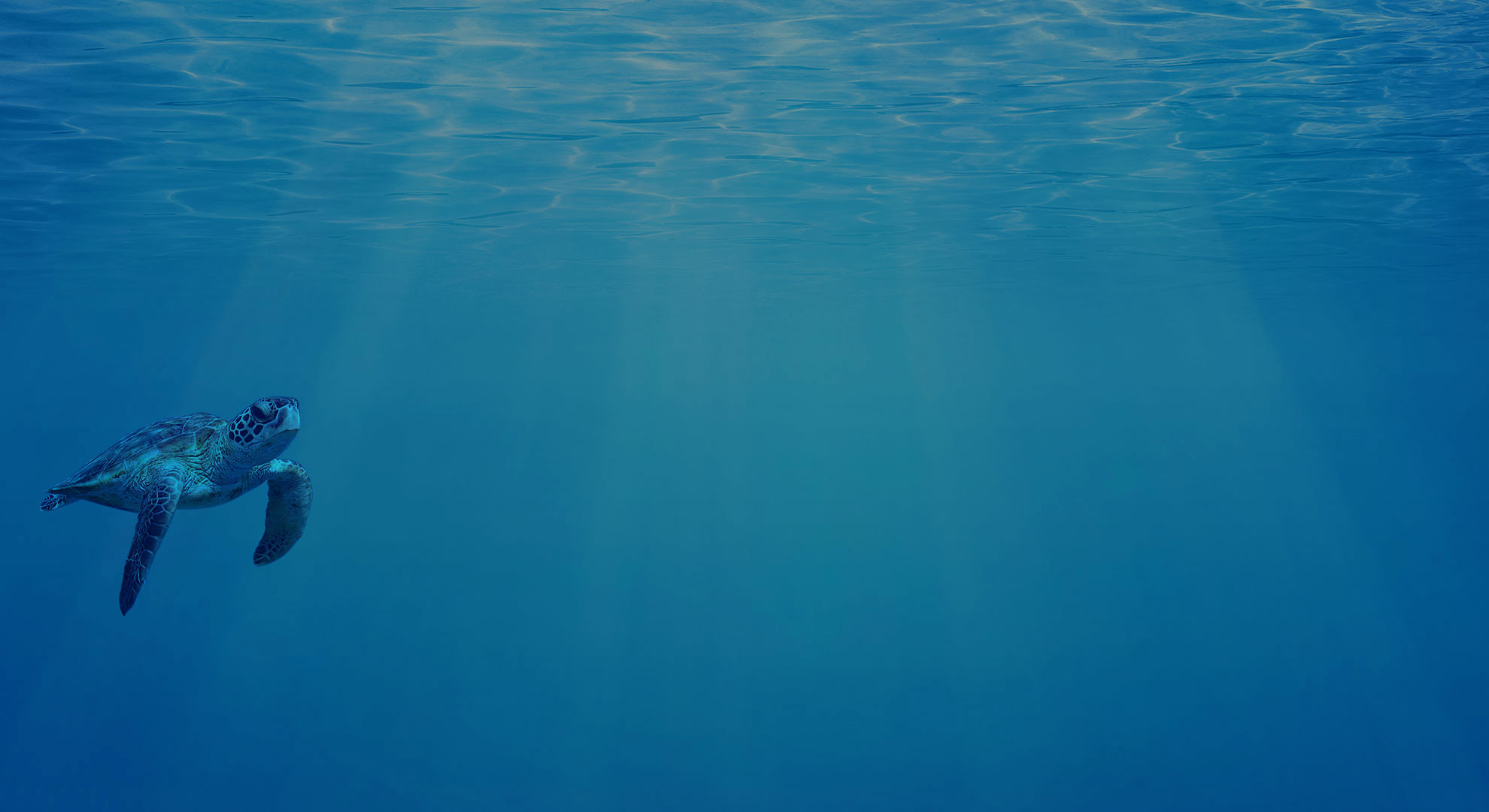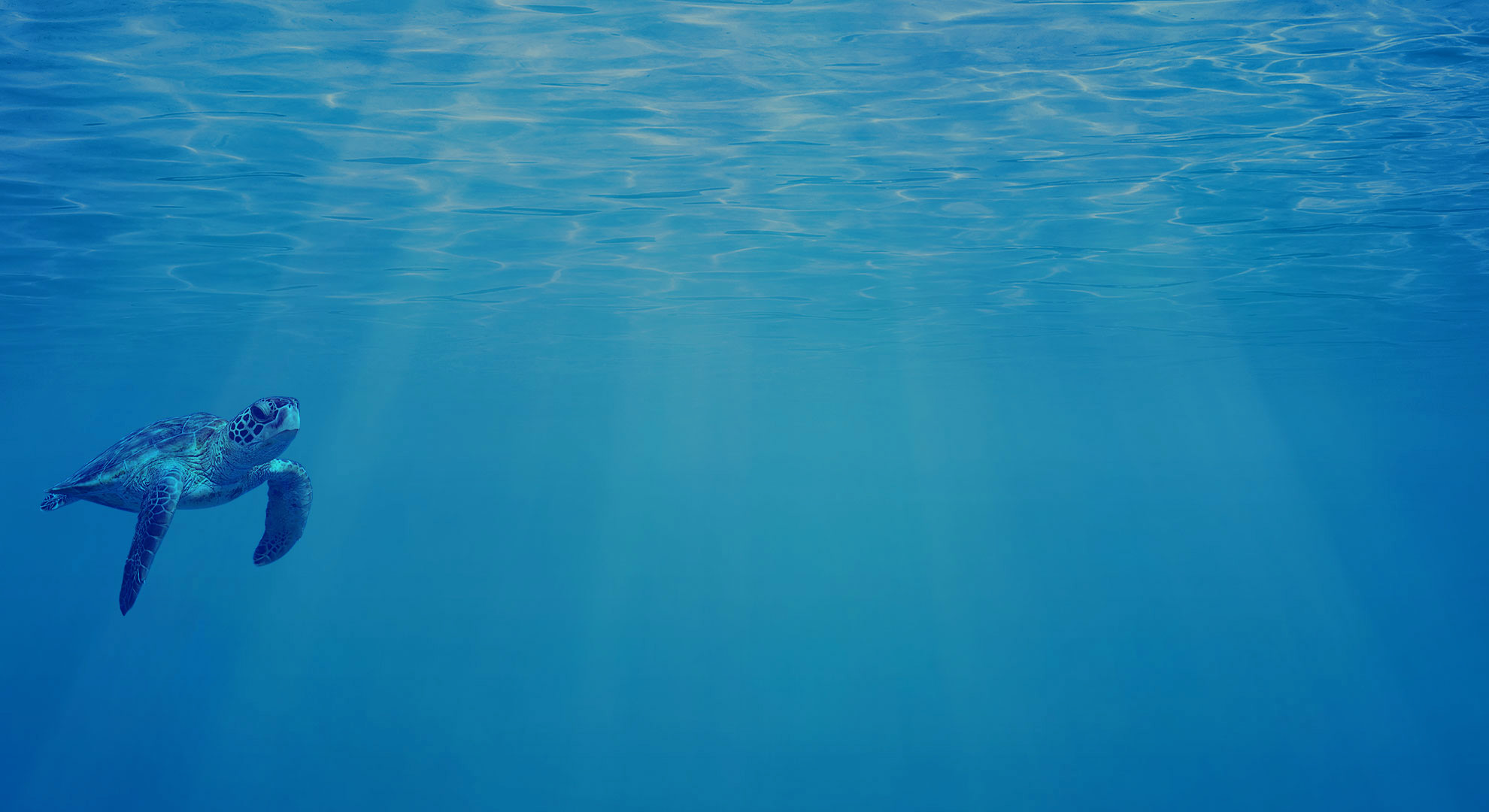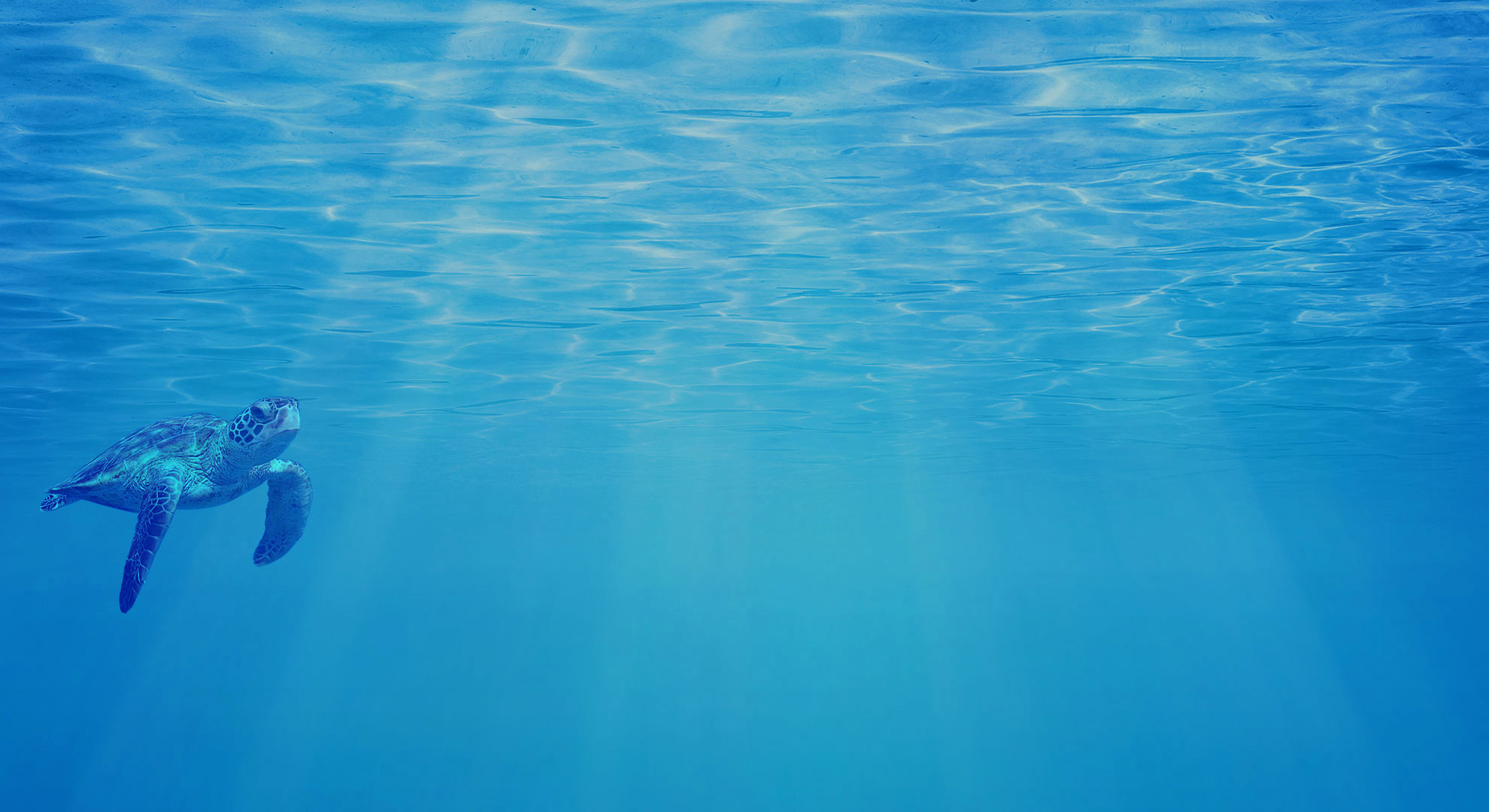Information
休診日情報
- 4月休診日
通常通り診療しています
Schedule
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| 14:00~20:00 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | / |
休診日:日曜日・祝日
水曜日・土曜日の診療時間:9:00~13:00/14:00~17:00(●)
※受付は原則30分前で終了です。緊急の場合は電話でお問い合わせください。
・肛門科に関しては毎週水曜日の16:30のみの完全予約制です。
Payment Methods
お支払い方法

※各種クレジットカードがご利用できます。くわしくは当院までお問い合わせください。
Map
アクセス情報
〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨1-21-4
都営荒川線 巣鴨新田駅より徒歩1分、庚申塚駅より徒歩5分 JR大塚駅北口より徒歩8分
©2024 Sengoku Clinic. All right reserved.